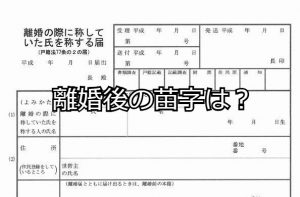婚姻費用請求とは?


こちらでも簡単にご案内しましたが、離婚前の別居時の費用であっても、婚姻関係が継続していれば、収入の少ない配偶者から収入の多い配偶者に対して生活費の請求が原則として認められる「婚姻費用分担請求」が認められます。
「離婚する予定だから」とか「喧嘩しているから」とかの理由で請求を拒むことはできません。離婚前提でも婚姻期間中であれば、婚姻期間中の生活費となりますので、請求があれば一定の条件のもと支払わなければいけません。ここでは婚姻費用について詳しくまとめてみました。
1.婚姻費用を決める方法
婚姻費用の金額はおおまかな基準があって、その基準でほぼ決まります。
「算定表」(養育費・婚姻費用算定表)と言う「基準額表」です。家庭裁判所での調停や審判で、婚姻費用の金額を決める時に参考にされています。
家庭裁判所では、基本的に、この算定表を基に婚姻費用の金額を決めています。別居をする場合、あらかじめ算定表を確認することで夫に請求できる金額の目安を知る事ができます。
算定表の見方
①見方(基本)
算定表は横軸に請求者(権利者)の収入、縦軸に支払い義務者の収入が年収で記載されており、それぞれの該当する金額から縦横に線を伸ばした合流点に記載された金額が相手に対して請求できる婚姻費用の目安になります。
【例】妻が夫に婚姻費用を請求する場合、妻は自分自身の収入から横軸(請求者)の部分を決定。次に夫の収入から縦軸の部分を決定し、交わるところが婚姻費用として請求できます。
②見方(未成年の子供がいる)
未成年の子供がいる場合、子供を監護している側の生活費指数が大きくなる分、婚姻費用の額は大きくなっていきます。そのため、「算定表」は未成年の子供の人数および年齢(0歳~14歳、15歳~19歳)に応じて複数の表となっています。
2.婚姻費用を請求できる期間
別居していても、婚姻関係が継続する以上は婚姻費用の請求が可能です。
つまり、いつまで(終期)費用の請求ができるかというと、「離婚が成立するまで」ということになります。またいつから(始期)請求できるかというと、「別居したときから」と思われがちですが、裁判所では、「調停で婚姻費用を請求したとき」からとなっております。つまり、調停を申し立てした時(始期)から請求できます。
3.婚姻費用を決定する方法
婚姻費用を決定する方法は下記の2つの方法がります。
①話し合いで決める方法
婚姻費用の金額を決める方法は必ず裁判や調停で決めなければいけない訳ではありません。夫と妻の話合いで決めても構いません。
話し合いで決める場合、重要なのは書面(合意書)で「記録」することです。口約束だけだと「言った言わない」となります。また書面(合意書)にしても、万が一、費用を支払わなくなる場合に備えて、公正証書にしておくのがベストでしょう。
※書面で記載(合意書または公正証書)する場合、専門家である弁護士や行政書士に依頼する事もできます。
②調停・審判で決める方法
当事者(夫婦)で話し合いが決まらない場合、次に調停をしていくことになります。夫婦での話し合いをせずに、最初から調停をすることも問題ありません。
調停は裁判所に「申し立て」をする事で開始することができます。この「申し立て」は、自分でする事もできます。裁判所へ行くと「申立書」の雛形がありますので、確認してみてください。
調停では、調停員を介して、配偶者の方と話し合うことになります。調停員という第三者を介する分、当事者同士の話し合いよりも、冷静に円滑に進めることが可能となります。
調停は裁判所で行われますが、裁判所の裁判官が一定の判断を下す「判決」をする事はありません。調停はあくまでも「話し合い」をする場で、調停員がそれぞれの言い分を聞いて、合意することができるか否かを探りながら話し合いを進めていく手続きなのです。
具体的な調停の内容
調停の申し立てがあると、日時が指定され、指定された日に当事者(夫婦または代理人)が家庭裁判所に行きます。家庭裁判所へ行くと…
- 1 まず最初に、申立て人が調停委員から呼び出され、調停委員から話を聞かれます。申立て人からの話をひととおり聞き終わると、申立て人は待合室に戻ります。
↓
- 2 次に、調停の相手方が調停員から話を聞かれます。相手からの話をひととおり聞き終わると、相手方は待合室に戻ります。
↓
- 3 次に、相手方が調停員との話合いが終わると調停員は相手方の要望、言い分を申立て人へ伝えます。次に申立て人の言い分を相手方に伝え・・・
↓
と、申立て人と相手方の言い分、要望を調停員を介して話し合いを進めます。
こんなやりとりは面倒ではないか?と思われますが、調停のメリットはこの当事者(夫婦)が顔を合わさず話を進めることにあります。つまり、調停委員を介して、話を進めるため、お互いが感情的にならず話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。
また調停委員も離婚に関してはある種の「プロ(専門家)」です。どのような解決をするのがいいのか、一定の提案をしてくれます。
調停のデメリットは、約1か月ごとに調停が行われるため、長ければ半年、1年…等かかることがあり、早急な離婚を望まれる当事者にはお勧めできない方法でもあります。
4.婚姻費用の不払い
別居中でも婚姻が継続されていれば、夫に『婚姻費用請求』ができますが、中には婚姻費用を支払わない方もいます。このような場合、離婚する際の財産分与を決めるとき、『婚姻費用の不払い分』を含めて決める事ができます。
不払いとなるケースは、故意に婚姻費用を支払わない場合の他、別居中に婚姻費用の手続きや話し合いをしなかったため、費用の額が決まらず、夫が全くあるいは十分な費用を負担しなかった場合、その分の婚姻費用を自分が立て替えたことになります。
この場合も離婚に際して財産分与の中でそれを精算してもらうよう請求することができます。
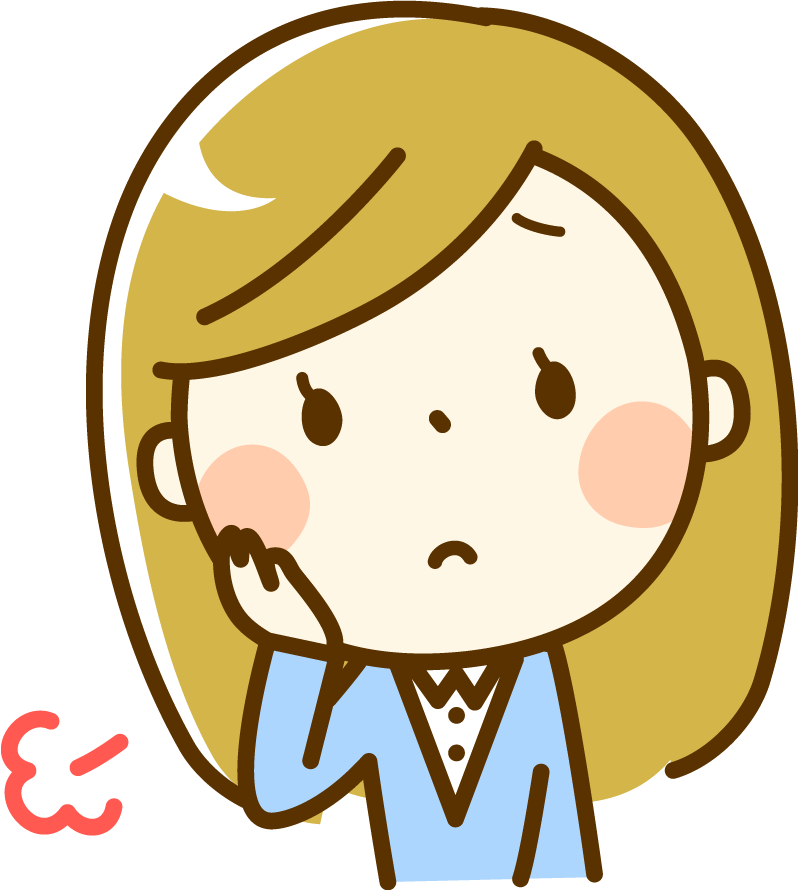
✔判例(過去の裁判の判決)
「離婚訴訟において、財産分与の額及び方法を定める場合、当事者の一方が適度を超える婚姻費用の清算のための給付も含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」としています。
5.不払い費用の清算の基準
では、どの位の額の婚姻費用を分担すべきなのか、大まかなな基準は…
- 双方の収入
- 資産状況
- 子どもの人数、年齢
- 生活水準
- その他の諸事情
上記を考慮して決まります。
例えば、婚姻費用として算定表に基づき、月20万円の支払い義務があったとき、2年間では480万円が未払いということになりますので、この分を財産分与の一部として請求することができます。
但し注意していただきたいのは、財産分与は裁判所が一切の事情を考慮して定めているとされていますので、財産分与の考慮事情としての婚姻費用の清算については、必ずしも算定表による算定額全額が認められるとは限らず、具体的な額や認める期間については、裁判所の判断に委ねられています。
また別居から離婚までの間の子どもの養育費の分担を離婚の訴えと一緒にして申し立てられることができるか否かについては、一緒に申し立てることが可能で、財産分与の際に、過去の子どもの養育費用相当分については、財産分与としてではなく、離婚後の養育費とあわせて、別居から離婚に至るまでの婚姻期間中の未払いの養育費として請求することができます。
6.婚姻費用の増額請求
いったん婚姻費用について、合意したり、裁判で決まった後でも、義務者が病気やけがで支払えなくなった、失職して収入がなくなった、一方の収入がかなり上がった、子どもの学費がかさむようになった等、双方にさまざまな事情の変化が起きることがあります。
こうした事情の変更があった場合には、当事者のいずれかからでも他方に対して、増額請求または減額請求を申し入れすることができます。そして、2人で話したっても合意に至らないときは、家庭裁判所に増額または減額請求の調停を申し立てることができます。
しかし、事情の変更があるからといって、いったん取り決めた額を義務者が勝手に一方的に減額してしまうことはできません。勝手に減額すれば不履行があるとして、給与等が差し押さえられる危険もあります。
離婚届・婚姻届の証人がいない…
当事務所が証人代行します
【 全国対応・証人2名4,500円 】
宮城県仙台市 よしだ行政書士事務所
代表: 吉田 貴之