親権者について


お子さんがいるご夫婦が離婚する場合必ず「親権」について決めなければいけません。ここでは「親権」に関しご説明します。
1.親権者の決定基準
原則、親権は夫婦の話合いで決定します。しかし、親権者の決定にあたっては下記の要素を考慮して決定すべきとされています。
- 子どもの利益を第一に考える
- 現実に毎日子どもの養育にあたることがより適切なのはどちらの親であるかという観点
一般的に親権者決定の判断基準や基礎となる事実は、離婚する前の別居中の監護者指定と原則同様とされています。
(1)こども側の事情
- 年齢、性別、心身の発育状況
- 従来の生活環境などへの適応状況
- 生活環境が変化することへの適応性
- 監護環境の継続性
- 子どもの意思や気持ち
- 子どもと父母や親族との情緒的な結びつき
- 兄弟姉妹との関係

(2)父母側の事情
- 意欲や愛情
- 監護の態勢
- 監護の実績や継続性
- 出生時以来の主たる監護者
- 子どもとの情緒的な結びつき
- 父母の年齢、生活態度、暴力や虐待の有無
- 居住環境、教育の環境
- 親族などによる監護の支援の有無
- 監護補助者がいる場合に、その監護は適切かどうか
- 監護補助者に任せきりにしていないか
- 監護開始の違法性の有無
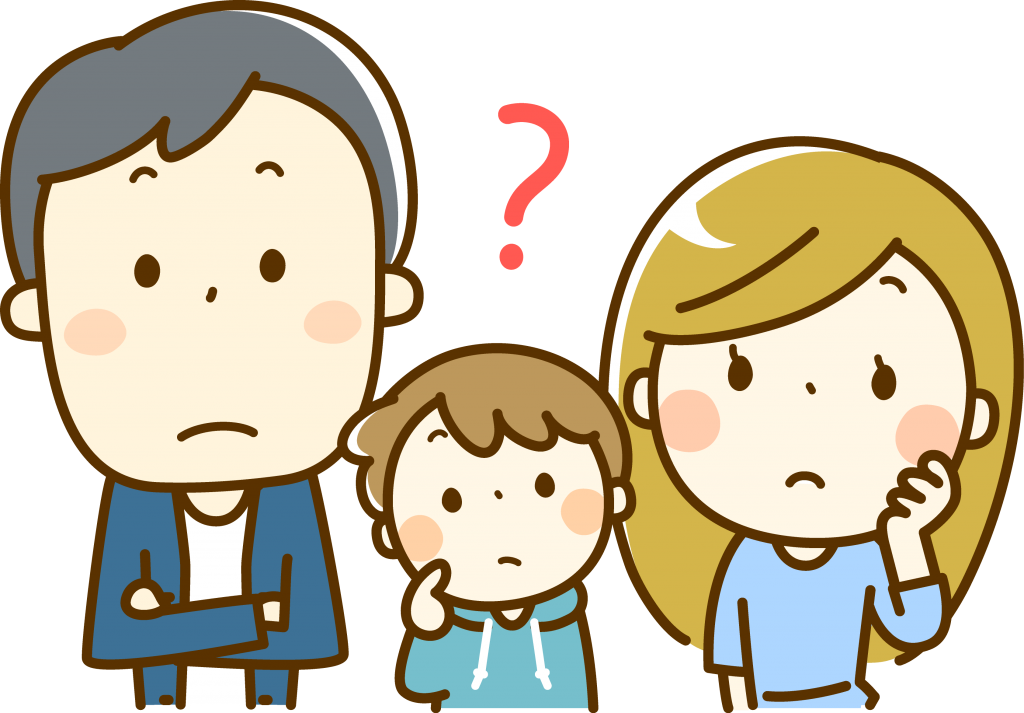
2.子どもの意思
「子どもの利益」を考慮する場合、一定の年齢に達した子どもについては、子どもがいずれの親と暮らしたいかという本人の意思を尊重することが必要です。子どもの権利条約においても、子どもの意思表明権を保障しています。
意思を尊重すべき基準となる年齢は、子どもによっても個人差がありますが、おおむね10歳前後からとされています。
しかし、子どもの意思尊重といっても、子どもの表明した移行がそのまま判断結果に直結するかというと必ずしもそうでもあれいません。子どもの年齢が高い場合には、現実問題として、子どもの意向に反して親権者を決定しても実効性が低いため、子ども自身の意向が判断へ及ぼす影響は少なくないですが、子どもの年齢やその発達の程度が低い場合、子どもの表面上の意思だけでなく、子どもの真意や心情について、しっかりと事実関係を整理して検討する必要があります。
3.面会交流に積極的か?
他方の親と子どもの面会交流に寛容になれるか、子どもに精神的安定を図れることができるか、これらも親権者指定の考慮要素となります。
しかし、面会交流が子どもの成長に与える影響にかんがみれば、大事な基準ですが、DVのあった事案などでは、被害者が加害者に対して寛容になることは容易ではなく、最重要の要素とされるわけではありません。
4.監護開始の態様
離婚前の別居時に、一方が一定期間単独監護を続けていたのに、他方が実力によって子どもを奪取したり、特段の事情の変更がないのに、面会交流の約束に反して子どもを返さないなど、監護開始の態様に違法性、悪質性があるときは、親権者としての適格性に疑義を生じます。
5.親権者について合意ができない場合
親権者について合意ができない場合は、協議離婚はできません。この場合、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停でも親権者について合意できない場合、調停全体が不成立となるので、調停に代わる審判がなされ、さらに審判でも決まらない場合、離婚の訴訟を提起することになります。
離婚届・婚姻届の証人がいない…
当事務所が証人代行します
【 全国対応・証人2名4,500円 】
宮城県仙台市 よしだ行政書士事務所
代表: 吉田 貴之


